スタジオジブリ作品の中でも、その悲劇性ゆえに深く心に刻まれる『火垂るの墓』。物語の主人公である清太と幼い妹・節子は、空襲で家を失い、飢えと孤独の果てに命を落とします。その痛ましい結末は、観る者すべてに深い悲しみと絶望を与えます。しかし、物語の序盤に描かれる彼らの生活は、決して「貧しい」ものではありませんでした。
この作品を初めて観る人の中には、「なぜ清太は、あんなにひもじい思いをしていたのに、最初からお金を持っていたの?」と疑問に思う人もいるかもしれません。実は、清太と節子の家庭は、戦時中としてはかなり裕福だったのです。
この記事では、『火垂るの墓』における清太の家庭の経済状況に焦点を当て、彼の父親の職業が海軍であったこと、そしてその裕福な暮らしが、彼らの悲劇にどのように繋がったのかを徹底的に解説します。清太の行動の背景にある、彼の育った環境や価値観を読み解くことで、この作品の持つメッセージをより深く理解していきましょう。
1. 清太の家庭の経済状況:当時の一般的な家庭との比較
『火垂るの墓』は、清太の家庭が当時の一般的な家庭と比べて、いかに裕福であったかを、いくつかの描写を通して示唆しています。
1.1. 貯金通帳と銀行口座
物語の冒頭、清太は母親から貯金通帳と7000円を受け取ります。
- 当時の7000円の価値: 1945年当時の7000円は、現代の価値に換算すると、およそ2000万円(当時の公務員の初任給を基準にした場合)に相当すると言われています。この金額は、当時の一般家庭が持てる金額をはるかに超えるものでした。
- 銀行口座の存在: 銀行口座を持つこと自体が、当時の一般家庭では珍しいことでした。この事実からも、清太の家庭が、経済的に恵まれていたことがわかります。
1.2. 母親の持ち物とドロップス
清太の母親が身につけていたものや、彼が節子に買い与えるお菓子も、その裕福な暮らしぶりを示しています。
- 着物の品質: 母親は、空襲の際に良い着物を身につけていました。これは、彼女が普段から質の良い衣服を身につけていたことを示唆します。
- ドロップス: 清太が節子に買い与えるサクマ式ドロップスは、当時、非常に貴重な嗜好品でした。物資不足の時代に、常にお菓子を食べられる環境にあったことは、彼らの家庭が裕福であったことの何よりの証拠です。
これらの描写から、清太の家庭は、戦時下の日本において、ごく一部の特権的な階級に属していたことがわかります。
2. 清太の父親の職業:海軍将校という社会的地位
清太の家庭が裕福であった最大の理由は、彼の父親の職業にあります。清太の父親は、海軍将校でした。
2.1. 海軍将校の社会的地位と給与
戦前の日本において、海軍将校は非常に高い社会的地位と、それに伴う給与を得ていました。
- エリート中のエリート: 海軍将校になるためには、厳しい試験と訓練を突破する必要があり、彼らは当時の日本におけるエリート中のエリートでした。
- 高い給与: 海軍将校は、一般の兵士や民間人と比べて、はるかに高い給与と手当を得ていました。この高い給与が、清太の家庭が裕福であった最大の理由です。
- 物資の優遇: 彼らは、一般の国民が物資不足に苦しむ中で、食料や物資の配給において優遇されていた可能性があります。
2.2. 父親への誇りと、清太の行動
清太は、父親を心から尊敬し、その職業に強い誇りを持っていました。
- 「お父さんは海軍さんや」: 清太が叔母の家で、海軍将校である父親の写真を飾っている描写は、彼の父親に対する誇りを示しています。
- 清太のプライド: この父親への誇りが、清太の行動に大きな影響を与えます。彼は、貧しい生活に陥りながらも、「自分は海軍士官の息子だ」というプライドを捨てきれずにいました。このプライドが、彼が「働くこと」を拒否し、叔母の家を出るきっかけとなった一因でもあります。
3. 裕福な暮らしがもたらした悲劇:清太の行動との関連性
清太の家庭の裕福な暮らしは、一見、彼らを救うはずのように思えますが、実は、それが彼らの悲劇を決定づける大きな要因となりました。
3.1. 労働への価値観のズレ
清太は、戦前の裕福な生活から、戦後の極貧生活へと、あまりにも急激な変化を経験しました。
- 労働への抵抗感: 彼は、父親のように立派な職業に就くことが当然だと考えており、肉体労働や日雇い仕事といった、当時の社会で最も貧しい人々が強いられていたような労働を、軽蔑していた可能性があります。この「労働への価値観のズレ」が、彼が定職に就こうとしなかった最大の理由の一つです。
- 生きるためのスキル不足: 彼は、裕福な家庭で育ったため、食料を確保したり、厳しい社会で生き抜くためのスキルを身につけていませんでした。これが、彼の無計画な行動や、盗みに走る原因となりました。
3.2. 叔母との対立の背景
清太と叔母の対立もまた、二人の価値観のズレから生じていました。
- 叔母の生活苦: 叔母は、戦時下の厳しい生活苦の中で、家族の命を守ることに必死でした。彼女は、清太に「働いて食料を得る」という、当時の常識的な生き方を求めました。
- 清太のプライド: しかし、清太は、叔母の言葉を、自分のプライドを傷つけるものだと感じました。彼は、自分たちが「施し」を受けていることを受け入れられず、叔母の家を出ることを選択しました。
4. まとめ:裕福な暮らしが、なぜ悲劇を生んだのか
『火垂るの墓』における主人公・清太の家庭は、彼の父親が海軍将校であったため、戦時中としては非常に裕福でした。しかし、この裕福な暮らしは、彼らを救うどころか、悲劇へと導く大きな要因となりました。
清太は、裕福な家庭で育ったがゆえに、厳しい社会で生き抜くためのスキルや、労働に対する正しい価値観を持っていませんでした。その結果、彼は働こうとせず、母親の貯金に頼り切った無計画な生活を送ってしまいます。そして、彼が抱いていた「海軍士官の息子」としてのプライドが、叔母の家を出るという、あまりにも甘い決断につながりました。
清太と節子の悲劇は、単に戦争がもたらしたものではなく、「裕福」がもたらした価値観のズレと、それによる社会からの孤立が、悲劇を加速させた側面もあるのです。この作品は、私たちに「裕福さ」が、時に人を救うどころか、生きる力を奪い、悲劇を生むこともあるという、深いメッセージを投げかけていると言えるでしょう。
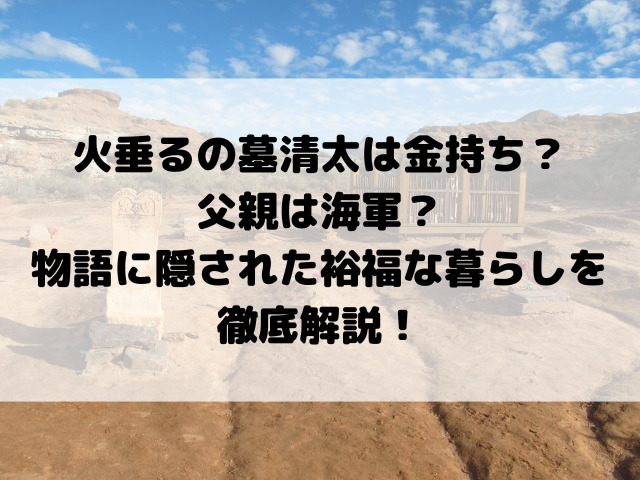
コメント