スタジオジブリの名作『もののけ姫』は、人間と自然、そして異なる種族間の対立と共存を壮大なスケールで描いた物語です。主人公のアシタカが旅の途中でたどり着くタタラ場は、鉄を作り、武器を生産することで栄える、力強く活気に満ちた集落として描かれています。多くの人々が働き、女性たちが中心となって活気づいている様子は、この物語における「人間の力」を象徴する重要な場所です。
しかし、このタタラ場を注意深く見ると、ある不自然さに気づきます。それは、多くの女性や男性が生活しているにもかかわらず、子供の姿がほとんど見当たらないということです。なぜ、これほど繁栄しているように見える集落に、次世代を担う子供たちがいないのでしょうか?そして、この事実に隠された「やばい」理由とは、一体何なのでしょうか?
この記事では、『もののけ姫』におけるタタラ場に子供がいない理由に焦点を当て、その背景にある深い意味を徹底的に考察します。タタラ場の「不自然さ」が暗示する、人間社会の闇と、この物語が持つメッセージを読み解くことで、この作品の魅力をさらに深く味わっていきましょう。
1. タタラ場の「不自然さ」:子供のいない集落
映画の中で、タタラ場には、多くの女性や病に侵された人々が、生き生きと働いています。しかし、そこに子供たちの姿はほとんど見えません。この事実には、いくつかの深い意味が隠されています。
1.1. 強制的に集められた女性たちの悲劇
タタラ場を牛耳るエボシ御前は、社会から見捨てられた人々を積極的に受け入れていました。
- 「病」を抱えた人々: エボシ御前は、ハンセン病患者といった、社会から差別され、追放された人々をタタラ場に集めました。
- 「遊女」たちの居場所: 彼女は、売られてきた女性たち、つまり「遊女」たちにも、働く場所と、生きるための希望を与えました。
タタラ場に集められた女性たちの多くは、過去に悲しい経験を抱えていました。彼女たちは、自らの意思ではなく、社会の都合によって集められた人々でした。そのため、彼女たちが子供を産み、育てるという、一般的な家族の形を持つことが難しかったと考えられます。
1.2. 過酷な労働環境
タタラ場での労働は、非常に過酷なものでした。
- 鉄を作る重労働: 女性たちは、鉄を作るために、一日中、鉄を精製する作業に従事していました。この作業は、非常に重労働であり、健康を害する可能性もありました。
- 「子育て」と両立できない環境: このような過酷な環境では、子供を産み、育てることは非常に困難でした。彼女たちは、自らの生活を維持するために、必死に働いていたのです。
タタラ場に子供がいないのは、単なる演出ではなく、その集落が持つ、過酷な現実を暗示しているのです。
2. タタラ場に子供がいない「やばい」理由とは
タタラ場に子供がいないという事実は、この集落が持つ、深い闇を暗示しています。
2.1. 「命」よりも「鉄」を優先する社会
タタラ場は、「命」よりも「鉄」を優先する社会でした。
- 「鉄」への執着: エボシ御前は、タタラ場を繁栄させるために、ひたすら「鉄」を作り続けました。彼女は、鉄の力によって、社会の秩序を変え、人間が自然を支配できると信じていました。
- 「次世代」への無関心: しかし、彼女は、鉄を作ることに夢中になるあまり、次世代を担う「子供」という、もっとも大切な「命」を育むことに無関心でした。彼女の社会は、未来を創造する力を持たない、一時的な繁栄にすぎなかったのです。
2.2. 「破壊」と「再生」の象徴
タタラ場に子供がいないという事実は、その集落が、「破壊」の象徴であることを示しています。
- 「森」の破壊: タタラ場は、鉄を作るために、森を破壊し続けました。森の神々や、もののけたちを殺し、自然の秩序を乱しました。
- 「再生」の力の欠如: しかし、その集落には、新しい命を生み出し、世界を「再生」させる力がありませんでした。タタラ場は、自らの繁栄のために、すべてを破壊する、自己完結的な社会だったのです。
この事実は、人間が、自然を破壊し、命を軽視し続ければ、いずれは、自らも滅びてしまうという、宮崎駿監督の強い警告を暗示しています。
3. アシタカとサンの存在が示す「希望」
タタラ場に子供がいないという、絶望的な状況の中で、アシタカとサンという二人の若者の存在は、**「希望」**の光となりました。
3.1. 「命」を尊ぶアシタカ
アシタカは、タタラ場の社会とは異なり、「命」を尊ぶ心を持っていました。
- 「呪い」と「命」: 彼は、タタリ神の呪いを受けながらも、その呪いを憎むことなく、命を大切にしました。彼は、タタリ神の苦しみを理解し、その命を救おうとしました。
- 「共存」への願い: 彼は、人間ともののけが、互いに殺し合うのではなく、共存できる世界を願っていました。彼は、タタラ場と森の間を、橋渡しする存在になることを選びました。
アシタカの存在は、タタラ場という「命」を軽視する社会に、新しい価値観と、希望をもたらしました。
3.2. 「愛」がもたらす「再生」
物語の結末で、アシタカとサンは、タタラ場と森という、異なる世界に属しながらも、**「共に生きる」**という選択をします。
- 「愛」という力: 二人の愛は、人間と自然、そして「破壊」と「再生」という、異なる世界を繋ぐ、強力な力となりました。
- 「新しい命」の象徴: 二人の愛は、新しい命を生み出す可能性を秘めていました。もし、二人の間に子供が生まれたとすれば、その子供は、人間ともののけ、両方の血を引く、新しい時代の象徴であったと言えるでしょう。
アシタカとサンの存在は、タタラ場という「命」を軽視する社会に、新しい「命」と、「再生」への希望をもたらしました。
4. まとめ:子供がいないのは、タタラ場の「限界」を暗示する宮崎駿監督からの警告
『もののけ姫』におけるタタラ場に子供がいない理由は、単なる偶然ではありませんでした。それは、タタラ場という社会が持つ、深い闇と、その限界を暗示する、宮崎駿監督からの強い警告でした。
タタラ場に子供がいないのは、社会から見捨てられた女性たちが、過酷な労働環境の中で必死に生きるために、子供を産み、育てるという選択をすることができなかったためでした。この事実は、タタラ場が、「命」よりも「鉄」を優先し、未来を創造する力を持たない、自己破壊的な社会であることを示しています。
しかし、この絶望的な状況の中で、アシタカとサンという二人の若者の存在は、「命」を尊び、人間と自然が共存できるという、新しい時代の「希望」となりました。彼らの愛は、タタラ場という「命」を軽視する社会に、新しい「命」と、「再生」への希望をもたらしました。
タタラ場に子供がいないという事実は、私たちに、自らの繁栄のために、自然を破壊し、命を軽視し続ければ、いずれは、自らも滅びてしまうという、宮崎駿監督の力強いメッセージを伝えているのです。
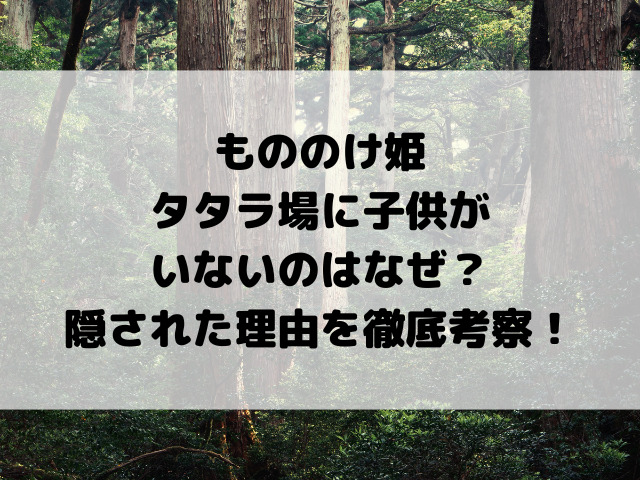
コメント